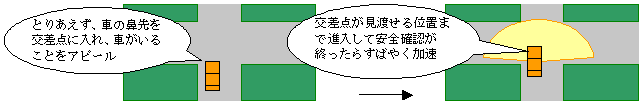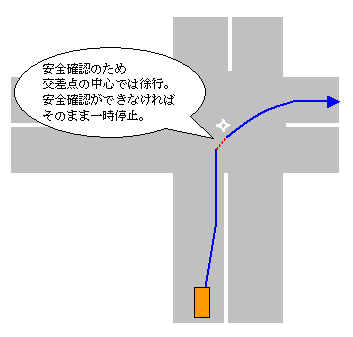次へ/前へ □ ホームページ > 安全運転の目次 > 段取りを良くすると運転が上手になる!
「段取りを良くすると運転が上手になる!」
最近「段取り」という言葉が流行っているようですね。
でも「段取り」って漠然といってもあまりピンとこないかもしれませんので具体的に。
例えばお料理の時
お料理をするときを思い浮かべると、まずレシピにしたがって材料を準備しますよね。
そして、手順どおり調理していくとできあがりますよね。
でも、レシピを見て料理を作っているうちは「その料理が自分のものになっていない」ということでもあります。
同じレシピで何度も料理をつくっているうちに要領がつかめてくると思います。
そう、要領がつかめてレシピなしで料理を作れるようになった時こそ、
自分で「段取り」ができるようになっているのです。
一旦段取りができるようになると、材料の1つがなくても代わりに別の材料を使うことで似たような味・食感を出せるようになりますし
大サジ2杯だったとしても、わざわざサジで量らず調味料の瓶からそのままお鍋に注ぎ込めるようになっています。
さらに作れる料理のバリエーションが増えていくと、コツがつかめてくるので
冷蔵庫の残り物を気にしながら毎日の献立を考えられるようになります。
例えばお仕事の時
お仕事などでは、まず見積もりやスケジューリング(アクションアイテムの洗い出し)が上手くないと
個々の作業がいくら上手くいっても、予定外の作業が発生すると
まったく納期に間に合わないということにもなりかねません。
多くの人はスケジュールを立てる時にいままでの経験から、
予備日を組み込んだりしてガチガチにならないように、
多少余裕を持ってスケジュールや予算配分を提案していると思います。
行き当たりバッタリだと、全てが終ってみないと分からないということになってしまい、
どこを頑張っていいのか分からず、最初から最後まで駆け足になってしまったり、
いつまで経っても終らないという、悪循環になってしまいます。
最初にざっくりでもいいのでスケジュールが立てられれば、
途中で不慮の出来事が発生しても全体に与える影響を把握できるので、すぐスケジュールの調整(リスケ)ができますよね。
運転する時
そして運転でいうところの段取りの良さは「判断のタイミング」で決まります。
タイミングには2つあって「早めに確認すること」と「その時に確認すること」に分かれます。
早めにチェックしなければいけないのは経路設定などです。
渋滞になりやすい道を避け走りやすい道を選んだり、休憩する場所を選んだりと
最初に大まかに全体的な流れを決めておいて、個々の状況での判断は必要な時にする。
車に乗る前から「ガソリンの残り大丈夫かな」と心配しても意味がないですよね。
それはエンジンを掛ける時に確認すれば済みますし、出掛けにガソリンスタンドに寄ればいいだけですから。
「その時」に確認することとしては、例えば見通しの悪い交差点での話をすると、
まず見通しが悪いので優先・一時停止標識に関わらず、交差点では安全確認が必要ですよね。
ここがミソで「いつ安全確認をするか」が問題です。
安全確認ができるのは交差する道路を見渡せる位置ですが
いきなりそこまで進入してしまうと、車の鼻先が交差点の中まで入り込んでしまい
交差する道から飛び出してきた車とぶつかってしまいます。
そのため、まず車が交差点にいることをアピールすめために車の鼻先を軽く見せる感じで
交差する道から車や歩行者が飛び出してきてもぶつからない位置で一旦停車します。
(交差点がある程度広ければ一時停止せずに徐行でそのまま進んでしまってもいいと思います。)
そのあとゆっくりと交差点を見渡せる位置まで進入していき、
確認が済んだらもう徐行する必要はありませんからすばやく加速して交差点を抜けるようにします。
同じように信号のあるような交差点で右折する場合も、
後続車の迷惑にならないように配慮しつつ、
歩行者や対向車の様子を確認できるように交差点中心まではすばやく進入します。
そして交差点中心で一呼吸置いて、右折先を確認するために一時停止するつもりで徐行します。
行けそうになかったら、そのまま一時停止ですし問題がなければ右折開始ですよね。
交差点を慎重に通過するのは、都合の悪いことに備えて、
見通しが悪ければ交差する道から車や自転車が飛び出してきても、
右折する時は対向車や横断歩道を渡る歩行者、自転車の飛び出しなどで
事故にならないように細かい段取りをしているのです。
ちなみに、判断するタイミングを早くすると段取りが良くなるような錯覚がありますが、
仮に200メートル先で右折しようと交差点を確認しても交差点の状況は刻々変化しているので
ほとんど意味がありません、通過しようとする瞬間の状況が大切なのです。
実は段取りが上手というのは、スケジュールを立てるのが上手いということで
予定外のトラブルによる多少の遅れも「折り込み済み」で
細かい部分で無理をしなくても良いように時間的な余裕が必要だということです。
当然、時間的に余裕があれば精神的にも余裕ができますよね。
また全体的に見れば、その道のりに比べて信号の2、3本くらいは誤差範囲でしょうから
無理に黄色信号を強行突破しようとする必要もなくなりますし、
割り込んでくる車がいても、1台や2台どうってことはないと思います。
最初に全体的なスケジュールを把握していれば、
個々の状況で一喜一憂しても、それらは全体的に見れば微々たる事だと気づくはずです。
もし、全体像が把握できないと細かいところばかりに目がいってしまい、小さいことに拘りやすくなります。
いい例が、渋滞中の二車線ある道を右に行ったり左に行ったり、と
隣の芝生は青い的発想で、ちょっとでも流れている車線を走りたがる人が当てはまると思います。
危険予測は段取り次第
例えば路線バス、追い越すか追い越さないか。
気分的に目の前に大きな車がいるのを嫌がるかもしれませんが
バスを追い越すときに事故に遭うリスクとバスを追い越して短縮できる時間を考えたり
追い越しがしやすいバス停まで待つのも段取りの良さと言えるでしょう。
横断歩道のペイントを見かけたら、歩行者を確認できる速度まで減速ですね。
対向車線が渋滞中は横断歩道でなくても歩行者が飛び出しやすいので、
センターライン側の間隔を広めにとって人影に注意します。
右折待ちの時に対向車の車間距離が中途半端でいけそうで、いけない状態が何度も続くと
焦ってしまい無理に右折してしまうことがあるかもしれませんが
段取りがキッチリできていると事務的に考え安全に右折できるタイミングになるまでストレスなく待つことができます。
見通しの悪い交差点を通過する少し前(5秒くらい前?)に飛び出しに遭遇すると
おっかなびっくり徐行してみたりするのだけれども
他の交差点では徐行するのをすっかり忘れてしまったり、、などなど。
そして、その時の気分によって確認を疎かにしたりして確認作業にムラがあると
まったく心の準備ができていないので突然の出来事に呆然としてしまい
事故にあっても何が起きたか分からずハンドルを握ったまま車から降りることができないかもしれません。
段取りが上手くないと、目の前の状況ばかりに目が行ってしまい、
客観的に見て無理をしなくてもいいところで無理をしてしまい事故の元になります。
段取りに慣れば、その時の不安定な気分によらずに、客観的にシチュエーションを把握できるようになります。
そして個々の確認作業の重要性を認識して、確認を面倒とは感じずに一連の流れの1つとして考えられるようになるので
スピーディーにかつ確認漏れがほとんどなくなっているハズです。
当然、段取りが良いと危険な状況になる前に、(確認する段取りで予め)スピードを落としたりできるので
ヒヤリハットを体験することが少なくなっていきます。
「安全運転」=「段取り運転」ということで、行き当たりバッタリでは運転が上手いとは言えないでしょう。
危険予測、すなわち「だろう運転」と「かもしれない運転」の違いはこのあたりにあります。
次へ 前へ 目次へ戻る
2000-2008 文:りあ